カルティベーション理論とは?これは人の歴史をつくる理論なのか!?
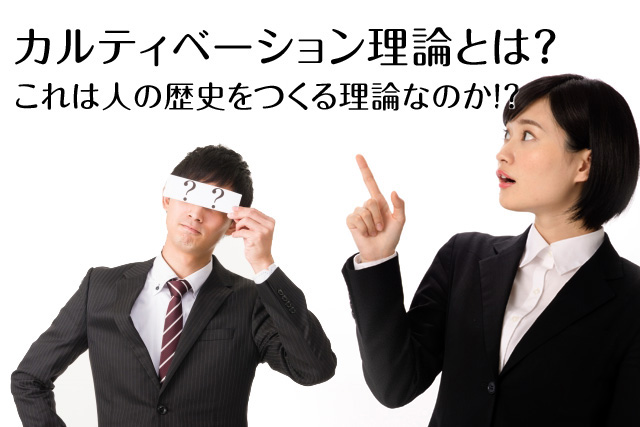
どうも、レタスです。
最近ネット上で「カルティベーション効果」という言葉を目にしました。
勉強不足の私は、全く聞いたことがない言葉でしたので、これを機に調べてみました。
というわけで、この記事は、
カルティベーション理論について知りたい人向けに書かれたものです。
カルティベーション理論とは?
カルティベーション理論は、日本語で「涵養理論(かんようりろん)」とも呼ばれます。
長年マスメディアに接することによって、その内容に影響を受けてしまい、現実とマスメディアとの境がなくなってしまうという理論です。
例えば「暴力で全て解決するような作品」ばかりを見ていると、暴力的な人間になる確率も高くなります。
こういった現象が起こる理論のことを、カルティベーション理論といいます。
昭和~平成のカルティベーション
昭和の頃から平成の初期にかけては、テレビによるカルティベーション効果が高い傾向にありました。
当時の若者たちはトレンディドラマで、出演者が着ているファッションや習慣をこぞって真似していました。
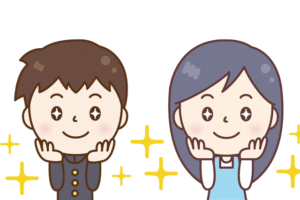
クリスマスにはホテルを予約しカップルで過ごすのが、誰もが憧れる過ごし方だったのです。
また昭和59年(1984年)は、紅白歌合戦の視聴率が78.1%もありました。
これは「大みそかは紅白を見る」というカルティベーション効果によるものでしょう。
この時代のカルティベーションは、特定された組織・人によって「つくられた流行」といえるかもしれません。
現在のカルティベーションは、テレビよりインターネットから発信されることの方が多い傾向にあります。
そして、その流行は使い捨てで、すぐに次の流行へ移り変わります。
消費者の趣味嗜好が多様化し、長期的なカルティベーション効果を得ることが難しい現代において、マスメディアはその舵を取ることが難しくなってきているのです。
そしてインターネットでは、利用者全員が視聴者であり発信者です。
視聴者が欲しがっている情報は、個人間で起きた「サプライズ」「トラブル」「感動体験」など「つくりものではなく、いかにリアルなものであるか」という事です。
テレビでも多くの人に影響を与える内容は、事件やスキャンダルなど、事実をもととした出来事が多いです。
「実体験を伴ったリアルさ」
それが流行りを形成するひとつの条件となっているように感じます。
カルティベーション効果は悪なのか
よく犯罪者が「暴力的なゲームをしていた」とか「アニメおたくだった」と言ったことが犯行に繋がったのではないかと言われます。

しかし何から影響を受けて犯罪に走ったということを、明確に立証できるわけではないので、この論理は浅はかだと感じます。
なぜなら戦闘シーンのある映画が好きな人はある一定数います。
しかし、その全員が暴行事件を起こしているわけではありません。
そう考えると、カルディベーション効果を受けやすい人は「自分の意見がない人」「思考停止に陥っている人」「物事に影響を受けやすい人」ではないでしょうか。
そして一見、悪くとらえられそうなカルディベーション効果ですが、善の側面もあります。
それは良いことに対して受ける影響です。
例えば
「松下幸之助に影響を受けて、起業し広く世の中の役にたつ会社を設立した」
だとか、
「マザーテレサの映画を見て、人に尽くす人生を送った」など
一概に悪い影響ばかりではないのがカルティベーション理論を語る上で忘れてはならないことです。
カルティベーション効果の影響力
私たちはマスメディアに限らず、広い意味でカルティベーション効果の影響から逃れることはできないでしょう。

カルティベーション効果の影響力を知っているからこそ、タバコを吸うシーンはテレビから極力排除されつつありますし、モラルを逸脱したり、犯罪を肯定する内容が放送されると視聴者からのバッシングに遭います。
それは私たちが母親の胎内から世の中に生まれた時から今まで、誰かの影響を受けずに育った人はいないからです。
だからこそ、ほとんどの人は無意識的にカルティベーション理論を理解しているのです。
誰かに影響を受けるという事は、先人の意志を受け継ぎ時代をつくっていくことにもつながります。
カルティベーション効果が、今の世の中をつくってきたといっても過言ではないのでしょうか。
スポンサードリンク
管理人のひとりごと
最近は新しい言葉がドンドン出てきて、知っていないとネットの記事すらまともに読むことができません。若い人が作り出す造語から、知識人が作り出す新しい専門用語まで、さまざまな言葉が生まれては消え、その中から長年にわたり使われ続け定着するものもあります。
言葉の専門家がよく「最近は言葉の乱れが目に付く」とか「本来の意味を知らない若者が多い」とか偉そうに言っていますが、
言葉は時代を反映して語られるものであり、流動的なものなのでそこに善悪をつけたり、正しい言葉、間違っている言葉とレッテルを貼るのは如何なものかと思います。
というのが私の持論です。
でも、文法や文脈(コンテキスト)が誤っているものは、確かにおかしいと思います。
しかし「複雑な意味を一つの単語で表現した言葉」というのはとても便利です。
まだ世の中に浸透していない言葉をついつい使ってしまうと、批判を受けかねないので注意が必要です(^^ゞ
これからも言葉の流動性を楽しみつつ、新しい言葉をインプットしていきたいと思います(o^-^o)
最後までお読みいただきありがとうございました!
執筆者:レタス
関連記事
-

-
どうも、レタスです。 私たちの生活に欠かせない「ガソリン」。 車に乗らない人でも、モノを送ってもらったり、バスに乗ることで間接的に関りを持っています。 このガソリンの価格って、どうやって決まるのでしょ …
-

-
彼岸花の開花条件は!?開花時期には生きるための秘策があった!
どうも、レタスです。 初秋に田んぼの脇やあぜ道など、さまざまな所で見かけるようになる彼岸花。 その独特なシルエットと“鮮やかな赤”は、日本の風景に情緒的な印象を与えます。 9月20日お彼岸の頃に咲くこ …
-

-
NHKの「みんなのうた」。 子どもの頃は気に入った曲を一生懸命覚えて、毎日のように歌っていました。 しかしその中にいくつか怖い歌があって、それも私の「みんなのうた」のよい思い出のひとつになっています。 …
-

-
Xジェンダーの特徴・診断を受ける前に知っておきたい3つのこと。
最近世の中でも徐々に認知され始めた「LGBT」。 L:レズビアン(女性同性愛者) G:ゲイ(男性同性愛者) B:バイセクシュアル(両性愛者) T:トランスジェンダー(性別越境者※) 上記のどれにも当て …
